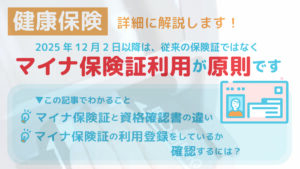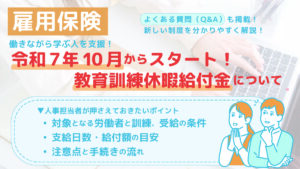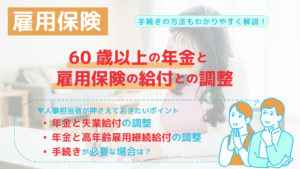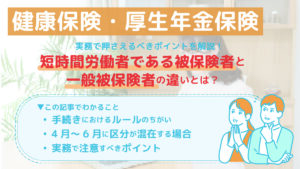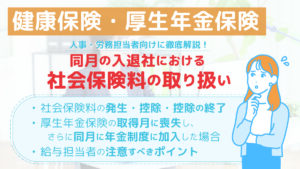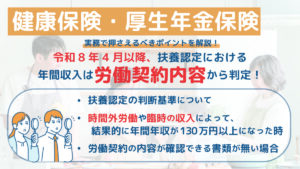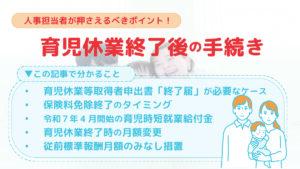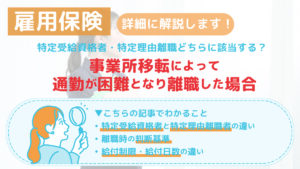2025年の改正でさらに充実!育児休業中の雇用保険給付金について解説します!
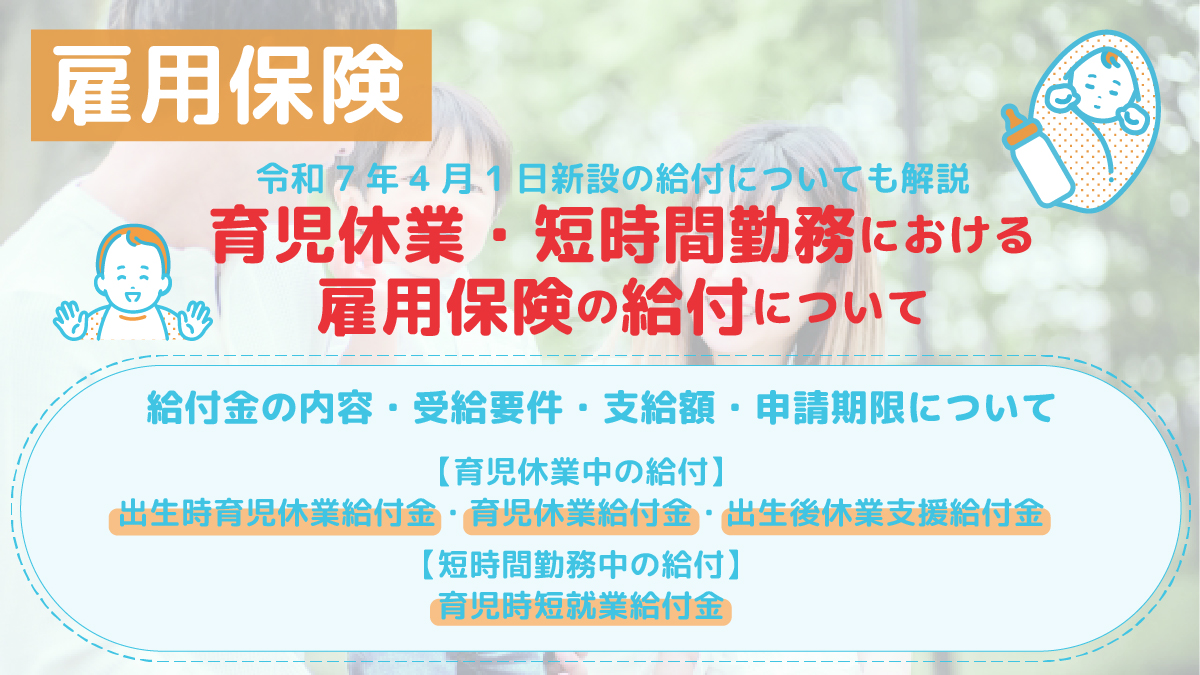
今回は育児休業中に受給できる雇用保険の給付金を見ていきたいと思います。
育児と仕事の両立を支援するため、雇用保険の給付金として、「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」に加えて、2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」が新たに創設され、さらに手厚い支援体制が構築されました。
これらの給付金は、子の誕生から育児休業、そして職場復帰後の短時間勤務まで、切れ目なく働く親の生活を支えることを目的としています。
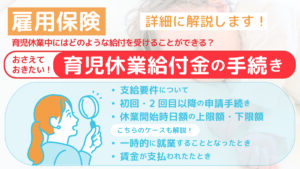
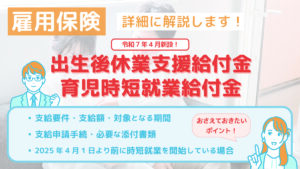
育児休業中の給付金
- 出生後休業支援給付金
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金
短時間勤務中の給付金
- 育児時短就業給付金
各給付金を見ていく前に、少し用語を整理しましょう。
産前産後休業(女性)
女性の出産日翌日から56日間の休業となります。
育児休業(女性)
出産日翌日から57日目以降は育児休業となります。
出生時育児休業(男性)
男性は出産をしないので、出産日または出産予定日から育児休業という名称となり、女性の産前産後休業に相当する期間の休業を出生時育児休業と呼びます。産後パパ育休とも呼ばれます。
男性の育児参加を促進し、共働き世帯における夫婦での育児分担を可能にすることを目的としています。
56日間のうち、28日までの休業を「出生時育児休業」と呼び、分割して2回まで取れます。
最初から28日を超える休業ですと、出生時育児休業ではなく「育児休業」となります。
育児休業(男性)
出産日または出産予定日から28日を超える休業
出産日翌日から57日目以降の休業
それでは、雇用保険の給付を見ていきましょう。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金とは出産日または出産予定日から56日間の女性の産後休業期間中に、男性が出生時育児休業(通算して28日まで)を取りますと給付されます。
女性は出産日翌日から56日間は産後休業であり、健康保険の出産手当金が給付されますが、男性は出産日または出産予定日から育児休業となりますので、女性の出産手当金の対象期間に給付されるようなイメージとなります。
要件
- 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)※分割した場合は合計で28日以内。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。(育児休業期間中でも、やむを得ず就労しなければならない場合に、柔軟に働くことができるようにこのような要件となっております)
- 期間雇用者の場合、子の出生日(※1)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(※2)が満了することが明らかでないこと。
※1 出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
支給額
出生時育児休業給付金の支給額
=休業開始時賃金日額(※)×休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また、当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金の総額を180で除して得た額をいいます。
休業開始時賃金日額の上限額は16,110円となります(令和8年7月31日までの額)。
育児休業給付金
女性は産後57日目からの育児休業、男性は出産日(または出産予定日)からの育児休業(※出生時育児休業を除く)について、女性男性ともに子が1歳になるまでの間、給付が行われます(パパ・ママ育休プラスは1歳2カ月まで)。
※出生時育児休業の場合は、出生時育児休業給付金となります。
育児休業給付金の対象となる育児休業は2回まで分割取得可能です。
3回目以降の育児休業については、原則育児休業給付金の対象とはなりません。
要件
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80 時間以上の)完全月が12 か月以上あること。
- 一支給単位期間中(※)の就業日数が10 日(10 日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間のことです。
- 期間雇用者の場合、養育する子が1歳6か月に達する日までの間(※1)に、その労働契約の期間(※2)が満了することが明らかでないこと。
※1 保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
支給額
育児休業給付金の支給額
=休業開始時賃金日額(※)×支給日数× 67%(育児休業開始から181 日目以降は50%)
※出生時育児休業給付金と同じです。
出生後休業支援給付金
産後パパ育休(出生時育児休業)に対して、出生時育児休業給付金に加えて支給される給付金が出生後休業支援給付金となります。
こちらは2025年4月に新設された新しい給付金となります。
両親がともに育児休業を取得することを促進し、育児休業給付と合わせて育児休業中の実質的な手取り収入を10割相当に引き上げることを目的としています。(社会保険料の免除、育児休業給付、出生後休業支援給付金を合わせると、就労時の手取りに近い金額となること。)
イメージ的には、被保険者(母)の産後休業中に夫婦そろって子どものために14日以上の休業を取っている方に、給付されます。
要件
- 被保険者(母)の産後休業中に、被保険者(父)が産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業を通算して14日以上取っていること。
上記①に代わり、配偶者の状態により、下記の要件を満たしても給付が行われます。
- 被保険者(母または父)の配偶者が子の出生日の翌日において、「配偶者(母または父)の育児休業を要件としない場合」(※)に該当していること。
※具体的には下記となります。
- 配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合、または災害により行方不明となっている場合に限ります。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
支給額
出生後休業支援給付金の支給額
=休業開始時賃金日額(※)×休業期間の日数(28日が上限)× 13%
※出生時育児休業給付金と同じです。
支給申請期間
出生時育児休業給付金/育児休業給付金・出生後休業支援給付金、は原則同時に申請を行います。
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。
ただし、出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から、申請可能となります。
申請先は会社の所在地を管轄するハローワークとなります。
申請に必要な書類
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 育児休業申出書・育児休業取扱通知書等(会社に育児休業を申し出た書類)
- 母子健康手帳(出生届出証明の頁)
※「配偶者(母または父)の育児休業を要件としない場合」に該当している場合は、他に書類が必要です。
申請期限
申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」およびその他添付書類を提出する必要があります。
以上、育児休業中の雇用保険の給付金ですが、ご紹介した内容はあくまで概要であり、他に細かな事項がございますので、詳細は下記厚生労働省の育児休業等給付のページをご確認下さい。
育児休業等給付についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
育児時短就業支援給付金については、別回にご案内いたします。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
育児休業給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。
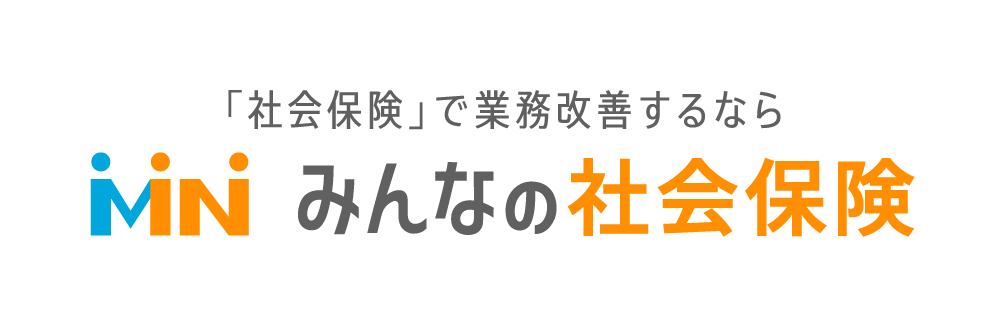
.jpg)