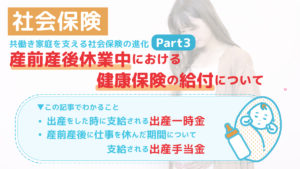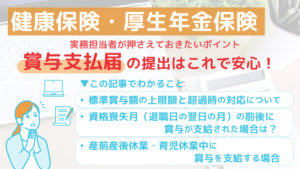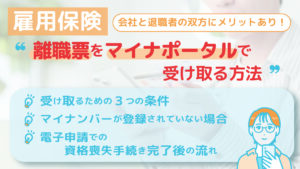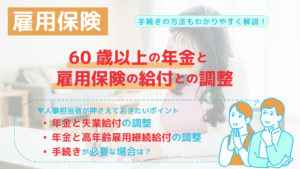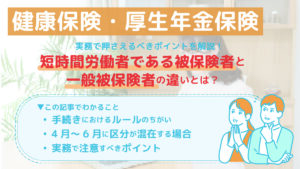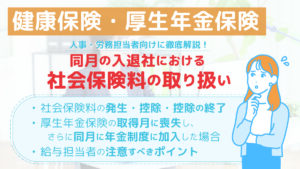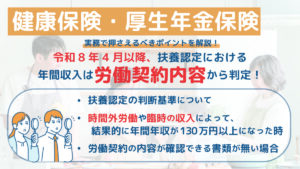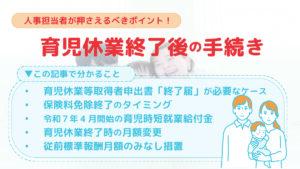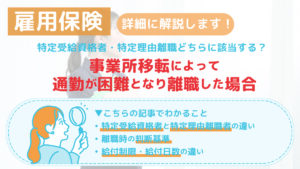介護休業給付金とは?対象者・支給条件・申請書類など、詳細に解説します!
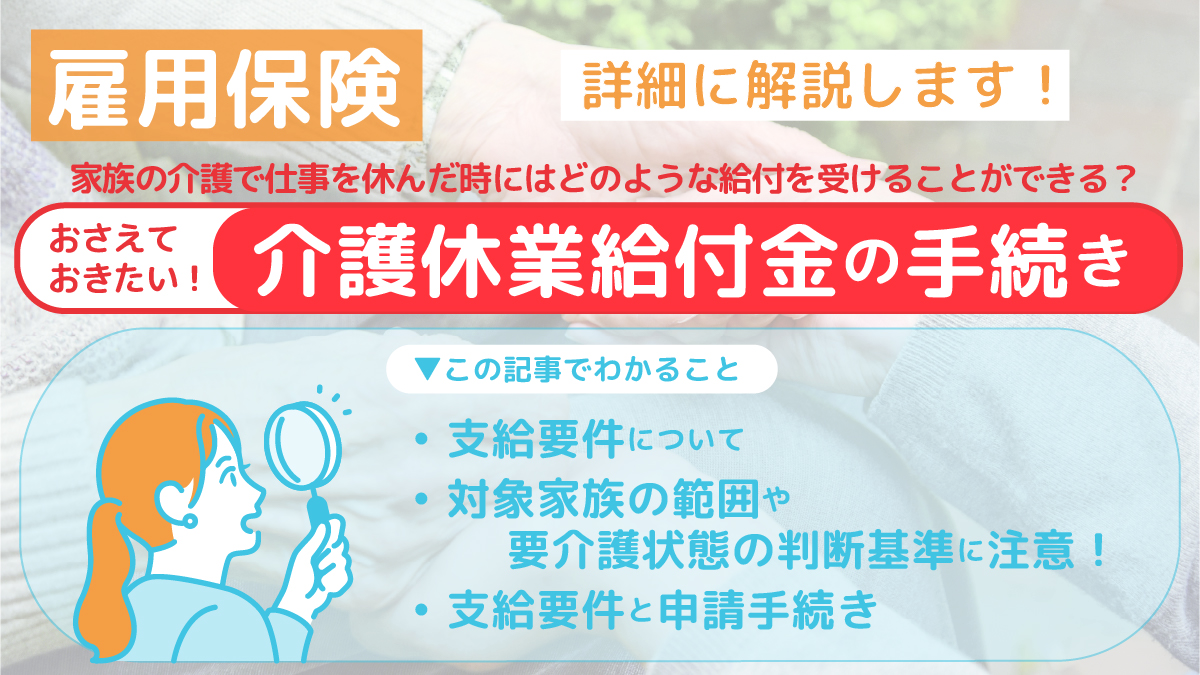
今回は介護休業給付金についてご説明させていただきます。
高齢化社会が進む中で、介護休業については制度の認識遅れが問題にもなっています。
今後、制度の利用は増えていくことが想定されますので、内容をしっかりと押さえておきましょう。
概要
雇用保険の被保険者が、対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと、93日を限度に支給される給付金となります。
支給対象者
雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(11日以上ない場合、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上)ある完全月が、12ヵ月以上ある必要があります。
※介護休業開始日前2年間に、疾病、負傷等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合、この期間を加えた日数(最大4年)となります。
※介護休業を開始する時点で、介護休業後に退職する予定の方については、支給対象とはなりません。
※有期雇用労働者の場合、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
支給対象となる介護休業
以下の①と②を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族につき、93日を限度に3回まで申請をすることができます。
①要介護状態である
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次の対象家族に限る)を、介護するための休業であること。
※要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となります。
【対象家族の範囲】
被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫
②被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これにより実際に被保険者が取得した休業であること
支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※支給日数は、休業終了日の属する支給対象期間は暦日数ですが、それ以外の支給単位期間については30日となります。
※賃金日額は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」によって、休業開始前の6ヵ月の賃金を180で除した額となります。
支給対象期間
介護休業開始年月日から介護休業終了年月日までの期間について、介護休業開始年月日から1ヵ月ごとの期間をいいます。
※介護休業期間中に対象家族が死亡した場合、死亡日当日まで介護休業給付金の支給対象となります。
支給申請手続き
介護休業から復帰後、介護休業の終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに申請をします。
なお、提出書類は以下の通りです。
~提出書類~
- 介護休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 介護休業申出書の写し(被保険者が事業主に提出した社内書類)
- 介護対象家族の氏名、性別、生年月日、被保険者との続柄(※)が分かる書類(住民票、戸籍謄本等)
- 介護対象者のマイナンバー(※)
- 賃金台帳、出勤簿
※介護対象家族と同一世帯の場合は、世帯全員分の住民票(続柄記載あり)を取得してもらうと良いです。
※介護対象者のマイナンバーは必須ではありませんが、被保険者と介護対象家族が同居している場合、介護対象者のマイナンバーも提出すると、被保険者との続柄確認書類が省略可能となります。ただし、介護対象家族の氏名、性別、生年月日が分かる書類の添付は別途必要です。
※介護休業期間中に対象家族が死亡した場合、戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書など、死亡日が分かる公的なものが必要です。
~2回目以降の申請を行う場合~
93日を分割して取得する場合、2回目以降の申請についても、1回目の申請の時と同じ提出書類が必要となります。
対象家族が要介護状態にあるかの判断基準
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となります。
介護休業中に就労した場合
1支給単位期間において、就労日数が10日以下でなければ、その支給単位期間について支給対象とはなりません。
また、介護休業終了日の属する1ヵ月未満の支給対象期間については、就労している日数が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
また、 1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合も、介護休業給付金の支給額は0円となります。(80%に満たない場合でも、賃金額に応じて減額される場合があります。)
介護休業は基本的には就業禁止のため、一時的臨時的に就労することは妨げないものの、考え方としては前もって決まった就業ではないというのが原則となります
<同じ対象家族について、複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合>
それぞれ支給要件を満たしているのであれば、介護休業給付金の受給は可能です。
<同じ対象家族について、93日分介護休業給付金を受給し、さらに同じ対象家族の要介護状態が変わったため再び介護休業を取得した場合>
既に93日分受給しているため、同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合であっても、再度介護休業給付金の支給を受けることはできません。
<過去に別の会社で介護休業をしている場合>
同一の対象家族について、他の事業主の下で介護休業をしたことがある場合でも、その日数は現在の勤務先での介護休業取得日数には算入されません。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
介護休業給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。
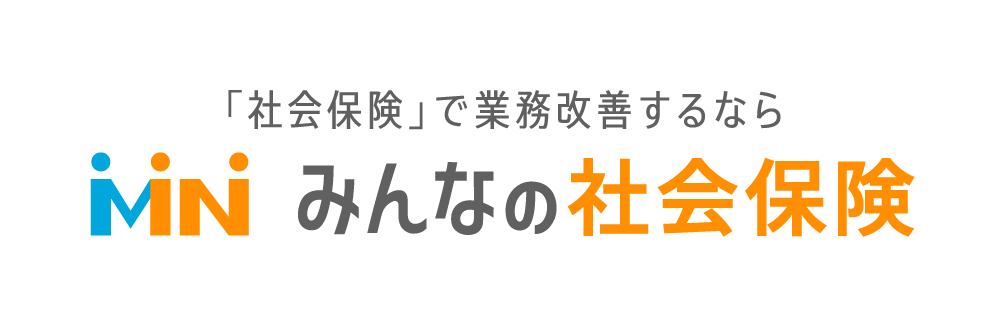
.jpg)