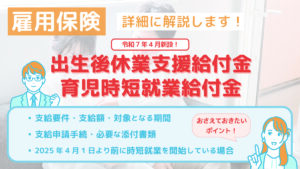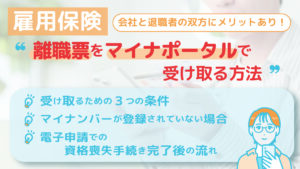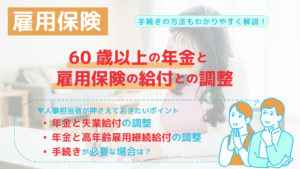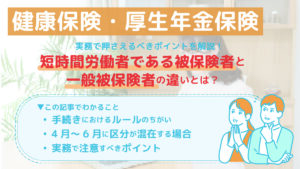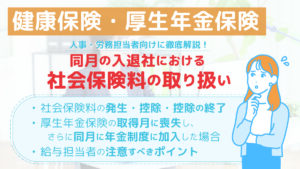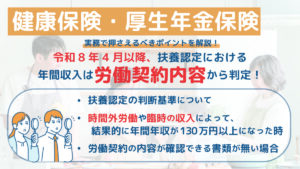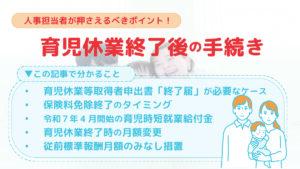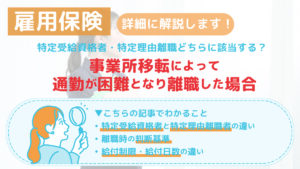賞与支払届と賞与にかかる保険料について:賞与支給時に必要な手続きを解説します!
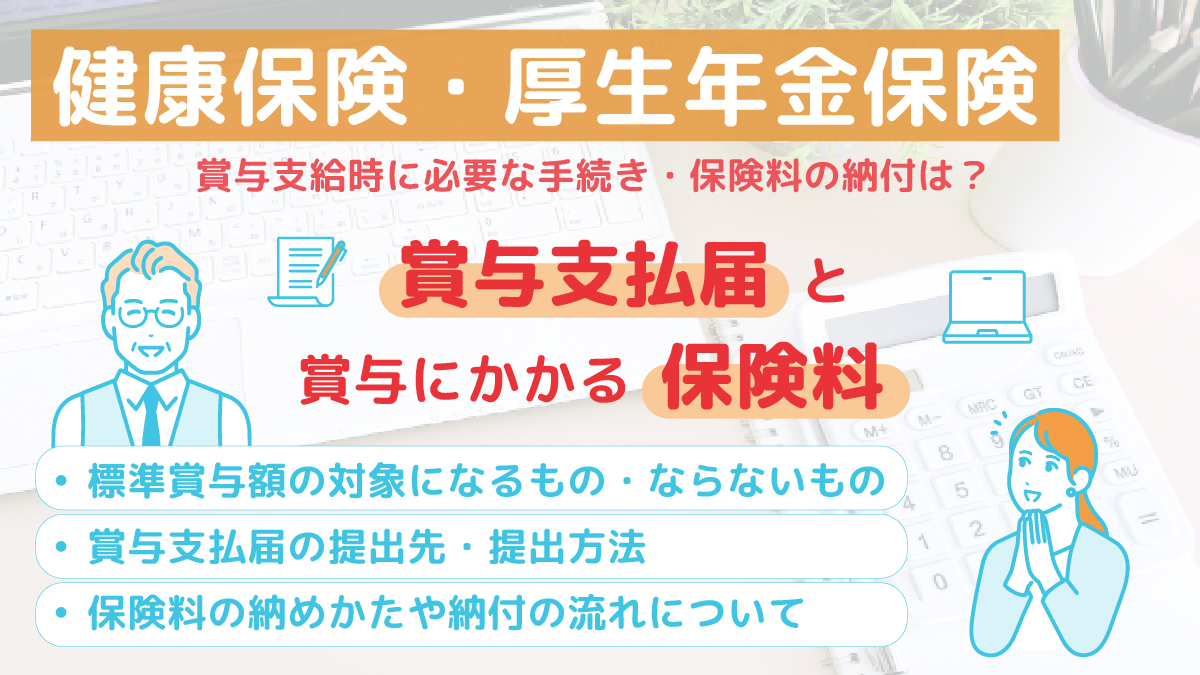
賞与を支給した際には、賞与支払届の提出が必要になります。
また、賞与にかかる社会保険料は、被保険者ごとの標準賞与額に、毎月の給与と同じ保険料率を乗じて計算され、原則、事業主と被保険者が折半で負担します。
今回は、実務担当者が押さえておきたい実務の基本とポイントを解説いたします。
ぜひお読みください。
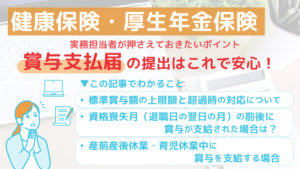
標準賞与額とは
年3回以下で支払われる賞与について、1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といい、保険料の計算は、「標準報酬月額・保険料額表」を使用するのではなく、「標準賞与額」に直接、保険料率を乗じて計算します。
この「標準賞与額」には、健康保険・厚生年金保険でそれぞれ上限額が設定されています。
標準賞与額の上限
| 健康保険 | 年度(保険者単位で4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円(※) |
| 厚生年金保険 | 支給1か月(同一月内につき2回以上支給されたときは合算)150万円 |
(※)「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出について
健康保険の上限である年573万円を超えて賞与を支給したら、管轄の保険者に「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出しなければならない場合があります。
「健康保険標準賞与額累計申出書」は、被保険者(従業員)から年間の賞与支給額が上限の573万円を超える旨の申告があったときに、会社が提出する書類です。
ただし、年度を通して在籍していた(被保険者整理番号に変更がない)被保険者の場合は、申出書の提出は必要ありません。転職して同一年度内に複数事業所で被保険者期間があり、それぞれの賞与支給額の合計が上限に達する場合に提出が必要になります。
転職後の会社は前職の会社で支給された賞与額を把握していないため、被保険者からの申し出に基づいて提出することになります
なお、申し出のあと、つまり上限を超えたあとに、賞与を支給する際は、再度申出書を提出しなければなりません。
転職の場合は分かりやすいですが、60歳以上の被保険者で、同日得喪の手続きをした方は特に注意が必要です。
同日得喪手続きをしたとしても、引き続き同じ会社に在籍しておりますが、被保険者整理番号は変更になっています。そのため、年金機構の登録としては、同日得喪前と後では別人の扱いになっています。(被保険者整理番号ごとに管理しているため。)同日得喪した被保険者についても、転職した方同様、該当する場合は「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出が必要になります。
標準賞与額の対象となるもの
標準賞与額の対象となる賞与とは、賞与、期末手当、決算手当など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいい、一般的に次のようなものがあげられます。
賞与の対象となるもの
金銭によるもの
- 賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末一時金、など賞与性のもので、年に3回以下支給されるもの。
- その他、定期的に支給されるものでなくとも、一時的に支給されるもの。
現物によるもの
- 賞与等として、自社製品など金銭以外で支給されるもの(金銭に換算)
賞与の対象とならないもの
- 年4回以上支給される賞与(この場合は、「賞与にかかる報酬(標準報酬月額の対象)」」になります。)
- 結婚祝金や大入り袋など、労働の対償とならないもの。
「通常の報酬」「賞与にかかる報酬」「賞与」について
名称の如何にかかわらず、2以上の異なる特質を有するものであることが給与規定や賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるものごとに判断されます。
年4回以上の支給と判断される条件
- 就業規則や給与規定などで年4回以上支給すると定められている。
- 7月1日前の1年間で4回以上賞与の支給が行われている。
この判断は毎年7月1日に行われる定時決定の際に見直されます。したがって、賞与の支給回数を変更する場合は、この始期を考慮して計画を立てる必要があります。
7月2日以降に賞与にかかる諸規定が新設された場合
年間を通じて、4回以上の支給が客観的に定められているときでも、次の定時決定(7.8.9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は賞与として賞与支払届の対象となります。
賞与支払届の提出
事業主は、賞与を支給した時は、「被保険者賞与支払届」を支給日から5日以内に提出します。賞与支払予定月(年金機構や健保組合に登録されている賞与支払月)に賞与の支払いが行われなかった場合には、「賞与不支給報告書」を届出ます。
「総括表」については、年金機構では提出不要ですが、健保組合で提出が必要な場合があるので、ご確認ください。
賞与支払予定月の前月に、年金事務所より、賞与支払届の様式一式が、あらかじめ登録された事業所あて送付されます。
- 届出用紙で提出する事業所
賞与支払届、賞与不支給報告書 - 電子媒体(CD,DVD等)で提出する事業所
被保険者の氏名、生年月日等を収録したCD-RW(ターンアラウンドCD希望の事業所)、賞与不支給報告書
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の事業所
事務センター(管轄年金事務所)へ提出 - 組合管掌健康保険(健康保険組合)の事業所
事務センター(管轄年金事務所)と健康保険組合の2カ所に提出
令和2年4月から、電子申請の義務化が始まっています。
政府全体で行政手続きコスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進が図られており、その取り組みの一環として、資本金等の額が1億円を超える等の特定の法人の事業所が社会保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行うことになっています。
義務化となっていない事業所であっても、業務効率化の観点から、電子申請で行うことが推奨されております。
賞与にかかる保険料について
賞与にかかる保険料は、各被保険者の標準賞与額に、毎月の給与にかかる保険料率と同じ保険料率を乗じて計算します。原則として事業主と被保険者が折半負担します。事業主は、被保険者負担分を賞与支払時に控除することが出来ます。
保険料の納め方
事業主から提出された「賞与支払届」にもとづき、賞与にかかる保険料と毎月の給与にかかる保険料を合算した保険料額が納入告知書により通知されますので、事業主は納付期限(月末)までに納付します。
年金機構の増減内訳書について
(希望する)事業主に対して毎月送付される文書(現在はオンライン上で確認)で、健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の増減内容を詳細に記載したものです。
この内訳書には以下の主要な情報が含まれています。
| 集計欄 | 個人別内訳から算出された保険料の増減額、標準報酬月額、標準賞与額などの情報 |
| 基本保険料(基本拠出金) | 前月末現在の保険料および拠出金。 |
| 本月増減額 | 当月の保険料変更額。 |
| 前月までの精算額 | 過去の調整が必要な金額。 |
| 本月充当額 | 前月からの繰越充当額や当月分に充当した額 |
| 既告知額と告知額 | 以前の告知額と現在の告知額。 |
| 個人別内訳 | 被保険者ごとの異動内容に基づく増減額。 |
増減内訳書は、事業主が従業員の社会保険料の変動を把握し、適切に管理するための重要な文書です。特に、従業員の入退社や給与変更などによる保険料の変動が正確に反映されているかを確認します。
賞与支払月と保険料納付の流れ
例:賞与支給日が12月10日の場合
賞与支払届提出日:12月15日(支給日より5日以内)
標準賞与額の総額+毎月の標準報酬月額の総額について、納入告知書が送付されます(賞与支払届の提出日の翌月20日前後)。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
オフィスステーションでは「賞与支払届」の電子申請をはじめとした各種手続きが、見やすい画面と直感的な操作でスムーズに行えます。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。
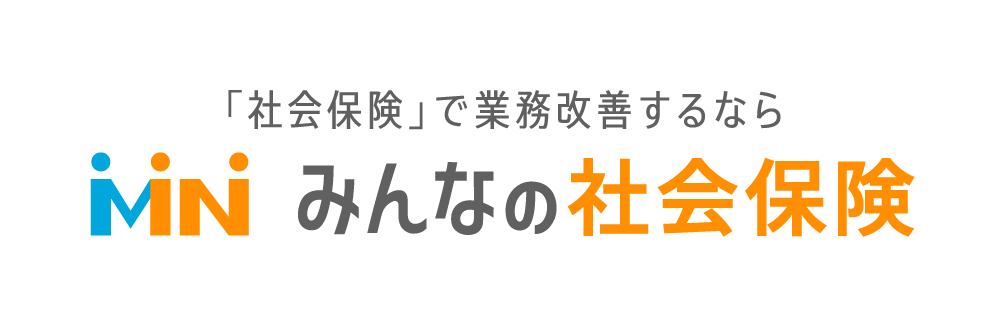
.jpg)