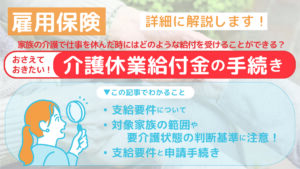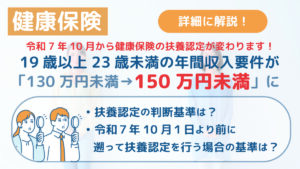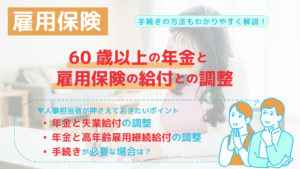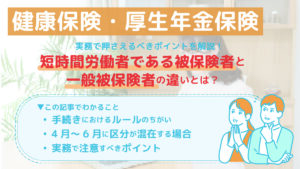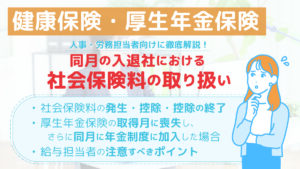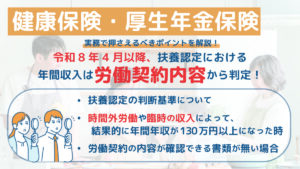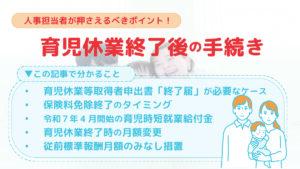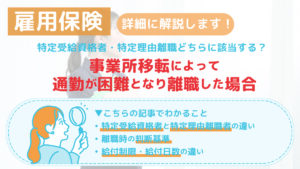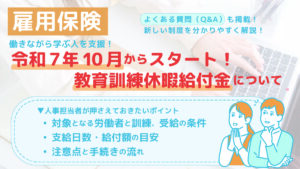賞与支払届提出時のイレギュラー対応について、詳細に解説します!
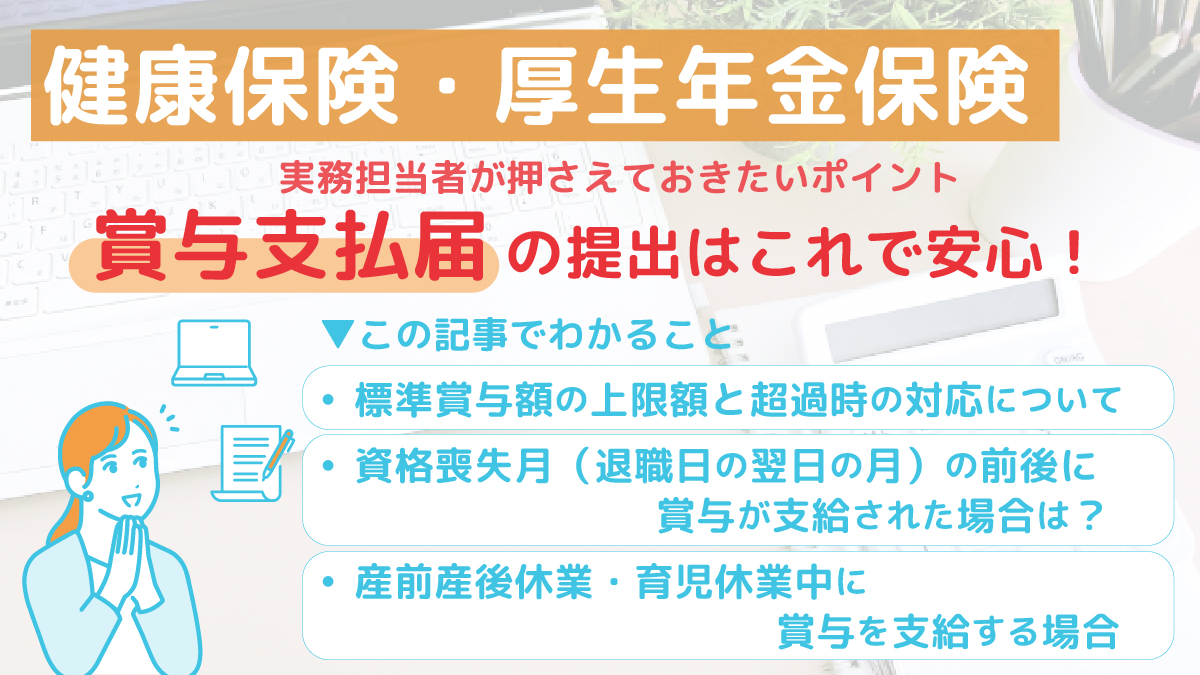
賞与を支給した際には、賞与支払届の提出が必要になります。
今回は、賞与の支給額が上限を超えた場合、資格喪失月に支払った場合、産前産後休業・育児休業中に支給する場合など、イレギュラー時の取り扱いについてご説明しています。
ぜひお読みください。
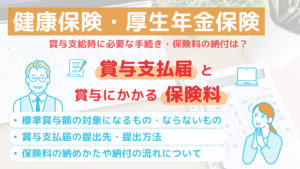
賞与支払届の留意事項
賞与額が上限を超えた場合
健康保険の標準賞与額には、年度(4月1日~翌年3月31日)で573万円という上限が設けられています。
この上限を超えた場合の対応は以下の通りです。
≪上限超過時の保険料計算≫
- 年度累計で573万円を超えた場合、超過分には健康保険料はかかりません。
例えば、6月賞与で400万円、12月賞与で500万円の賞与を支給した場合、最初の400万円全額と、次の500万円のうち173万円までが健康保険料の対象となり、残りの227万円には、健康保険料がかからないということになります。
≪手続き≫
- 同一年度内に転職して複数の事業所で被保険者期間がある場合、累計が573万円を超えるときは、「健康保険標準賞与額累計申出書」を保険者に提出する必要があります。
提出しないと年金機構では同一人物と判定出来ず、自動計算されません。そのため、上限を超えた分についての健康保険料を請求されてしまいますのでお気を付けください。 - 会社は前職で支給された賞与額を把握できないため、被保険者からの自己申告(申し出)により申出書を作成・提出します。
- 同一の事業所で累計額が上限を超えた場合は、自動計算されますので、申出は不要です。
ただし、60歳以上の方が定年後再雇用で同日得喪の手続きをしたために、年度内で被保険者整理番号が変更になった場合は、自動計算されませんので、転職した時と同様に「健康保険標準賞与額累計申出書」を保険者に提出する必要があります。 - 標準賞与額が年度を累計して上限(573万円)を超えた場合でも、賞与支払届には、実際に支払われた賞与額(1,000円未満切り捨て)を記入します。(保険料の徴収対象外の賞与も含めて記載します。)
「健康保険標準賞与額累計申出書」
提出の流れ
- 被保険者が、同一年度内の賞与累計が573万円を超えたことを会社に申し出る。
- 会社は「健康保険標準賞与額累計申出書」を作成し、年金事務所または管轄の保険者へ提出する。
- 申出書提出後、上限を超えた分の賞与については健康保険料の徴収対象外となります。
- その後も同一年度内に賞与が支給される場合は、その都度申出書の提出が必要です
≪注意点≫
- 上限は「保険者ごと」に判定されます。年度途中で健康保険組合が変わった場合は、それぞれの保険者ごとに累計します。
標準賞与額の累計は、全国健康保険協会または各健康保険組合等の保険者単位でおこなうためです。全国健康保険協会から健康保険組合へ転職した場合などは、賞与額の累計は行いません。 - 育児休業等で保険料免除中に支給された賞与も累計に含まれます。
資格喪失月の賞与支払届
資格喪失月(退職日の翌日が属する月)に賞与を支給した場合の「賞与支払届」の取扱いは、賞与の支給日と資格喪失日(退職日の翌日)の関係によって異なります。
~基本ルール~
以下のルールを基に、支給日と退職日(資格喪失日)の関係を必ず確認しましょう。
賞与支払届の提出が必要です。
この賞与は、標準賞与額の年度累計額に含まれますが、資格喪失月であれば社会保険料の控除は不要です。
賞与支払届の提出は不要です。
この場合、既に社会保険の被保険者資格を喪失しているため、届出対象外となります。
資格喪失日は翌月1日となるため、退職月の賞与は通常通り賞与支払届の提出と社会保険料の控除が必要です。
産前産後休業、育児休業等期間中の支払い
- 産前産後休業や育児休業中でも、就業規則や労働契約で「賞与の支給基準」「算定期間」「支給条件」などが明確に定められている場合は、休業中であっても支給基準を満たす全従業員に賞与を支給する必要があります。
- 休業期間が賞与の算定期間に含まれている場合、その期間は「不就労」として日割り計算で減額することは認められています。
ただし、「休業したこと自体」を理由に減額や不支給とするのは法律違反(育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等)となるため注意が必要です。 - 産前産後休業・育児休業中は、事業主が年金事務所に申し出ることで健康保険・厚生年金保険料が免除されます。これは賞与にも適用され、該当期間中に支給された賞与の社会保険料は控除されません。
- 免除対象となる期間は、「休業開始月から終了月の前月まで」です。
- 令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
そのため、賞与支給月の月末が育児休業期間に含まれているという状況だけでは、賞与の社会保険料が免除にならなくなりました。 - 産前産後休業、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与については、保険料の対象となりませんが、年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要です。
70歳以上の方に賞与を支払った場合(厚生年金)
- 70歳以上の従業員に賞与を支給した場合も、被保険者賞与支払届(「70歳以上被用者賞与支払届」)の提出が必要です。
- 「70歳以上被用者賞与支払届」を提出することで、賞与額が在職老齢年金の支給調整に反映され、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、老齢基礎年金(国民年金部分)は減額されず、全額受給できます。支給停止の対象となるのは老齢厚生年金部分のみです。
- 70歳以上になると厚生年金保険の被保険者資格は喪失しているため、厚生年金保険料の徴収はありません。ただし、年金の支給調整(在職老齢年金)の対象にはなります
- 賞与支払届の提出内容(賞与額)は、在職老齢年金の支給額調整に反映されます。
届出書の記載方法
- 賞与支払届の「備考」欄にある「70歳以上被用者」に○(丸)を付けます。
- 「個人番号(マイナンバー)」または「基礎年金番号」を必ず記載します。
保険料の取扱い
『厚生年金保険料』
- 70歳以上の従業員は厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているため、厚生年金保険料は徴収されません。
『健康保険料』
- 75歳未満の場合、健康保険の被保険者であれば、賞与から健康保険料のみ徴収します。
賞与が不支給だった場合
日本年金機構に登録した賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書」を提出します。
賞与支払予定月に変更がある場合は、変更後の賞与支払予定月を記入してください。
※令和3年4月より「賞与支払届総括表」が廃止になり、賞与不支給の際には「賞与不支給報告書」を提出することになりました。
提出しない場合、社会保険料の計算に誤りが生じる恐れがあります。
また、一定期間経過後、賞与支払届提出の督促がきてしまいますので、お気を付けください。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
オフィスステーションでは「賞与支払届」の電子申請をはじめとした各種手続きが、見やすい画面と直感的な操作でスムーズに行えます。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。
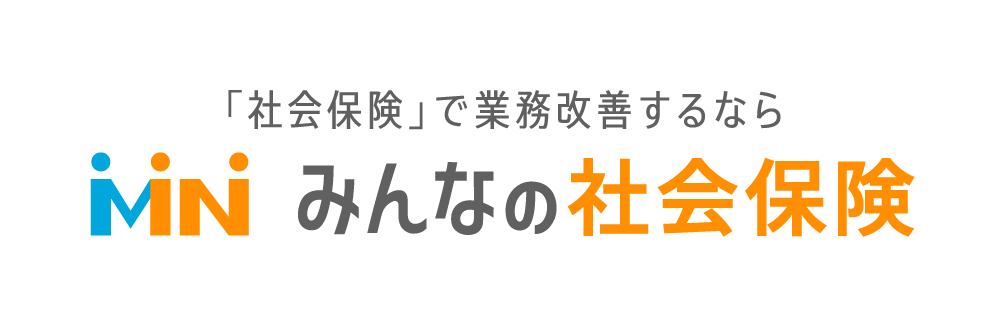
.jpg)