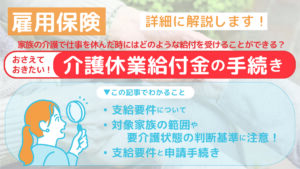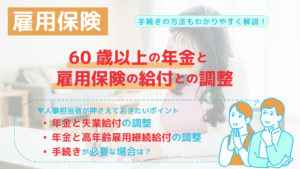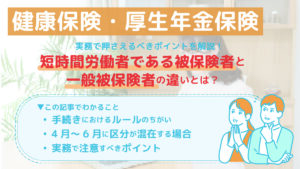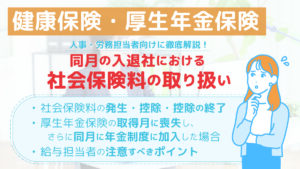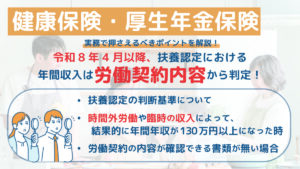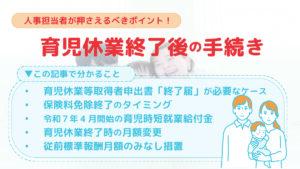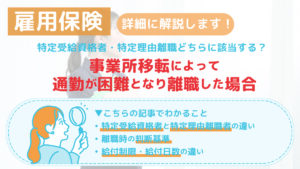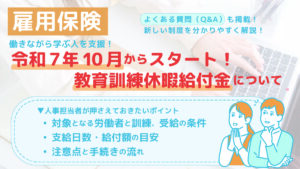【少子化時代における社会保険制度 Part3 】産前産後休業中の給付について確認しましょう!
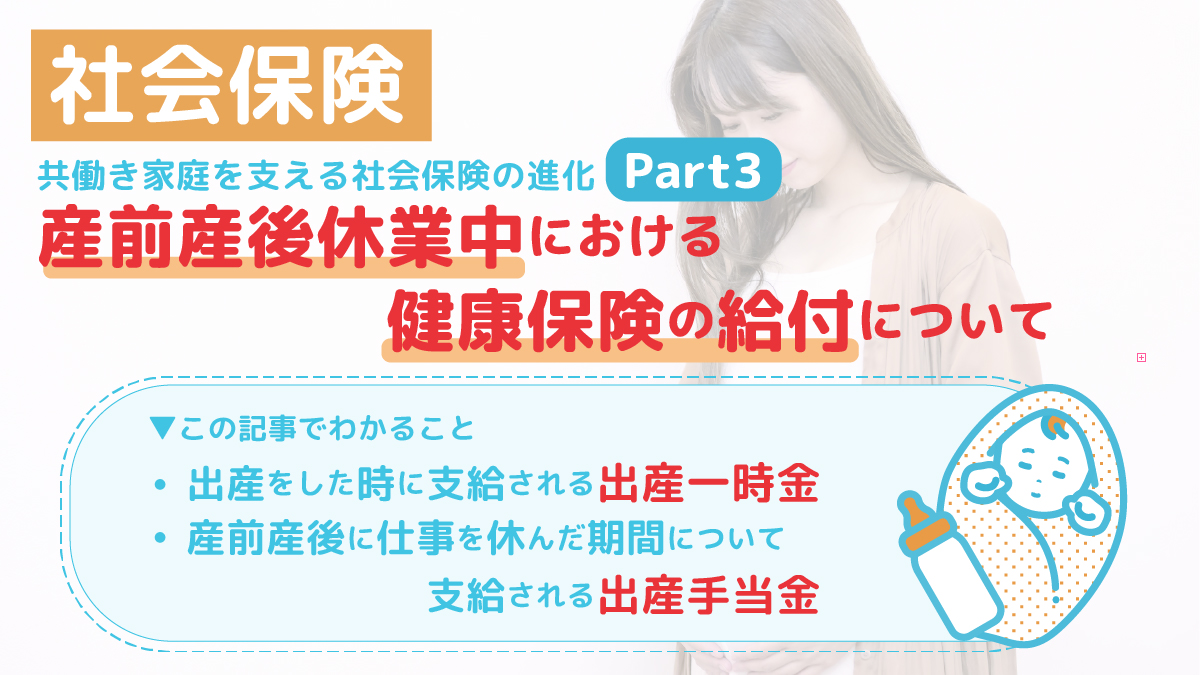
前回は産前産後休業における社会保険免除制度を見てきました。
今回は出産における健康保険の給付を見ていきましょう。
出産における健康保険の給付は2つあります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
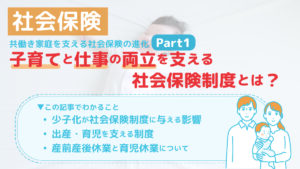
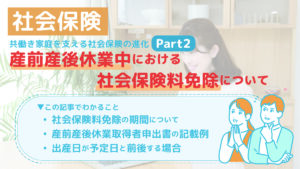
出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産をした時に、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児につき50万円となります。
(※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、または妊娠週数22週未満の出産の場合は48.8万円)
手続きは子を出産する病院で行います。
病院で手続きを行いますと、出産育児一時金が病院に支給され、被保険者の分娩費用に充てられ、出産時の費用負担の軽減となります。
不運にも死産となる場合、妊娠4か月(85日)以上の早産、死産、流産、人工妊娠中絶について出産育児一時金の対象となります。
こちらの一時金は被保険者でなくても健康保険の被扶養者であれば、受給することができます。
出産はその世帯単位でお金がかかることですので、被保険者の世帯として健康保険が一時金により経済的負担を軽減している仕組みとなります。
※産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
出産手当金
被保険者の産前産後休業期間について、出産手当金の支給対象となります。
産前産後休業期間中は給与の支給が無い状態となりますので、給与支給を前提に生活している従業員にとっては、生活を圧迫してしまいます。
そこで健康保険から給与の全額ではありませんが、給付が行われます。
さらに産前産後休業中の社会保険料は免除となりますので、保険料免除と合わせて出産手当金により、経済的な負担を軽減することとなります。
要件
出産手当金の支給要件は下記となります。
- 産前産後休業期間中であること
- 産前産後休業期間中に給与支給が無いこと
支給額
出産手当金の支給額は下記となります。
1日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給される日のことです。
1日あたりの額=30万円÷30日×3分の2=6,667円
仮に産前産後休業が98日ありましたら、6,667円×98日=653,366円となります。
【端数処理】
「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します
「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次の①②いずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均値
30万円※:支給開始日が令和7年3月31日以前の方
32万円※:支給開始日が令和7年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
出産が遅れ、産前産後休業が延びた時
出産が予定日より遅れますと、産前産後休業の内、産前休業の部分が延びます。
仮に予定日より10日遅れますと、産前休業も10日延びることになりますので、産前42日+延びた産前10日+産後56日の合計108日について出産手当金を受給することができます。
手続き
出産手当金支給申請書を協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。
届出は被保険者本人または会社のどちらでも結構です。
協会けんぽの場合、3枚1セットとなっております。
1枚目は被保険者が記入し、2枚目は医師または助産師の証明、3枚目は会社の賃金支給に関する証明となります。
産前分・産後分と分けて、または産前産後を一回で申請することができます。
書類のご用意はお早めにしていただくことをお勧めします。
申請書は下記をご参考になさってください。
【出産手当金支給申請書/協会けんぽ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
資格喪失後の出産手当金
産前産後休業中に退職する方について、退職後も出産手当金の対象となる場合があります。
要件としては下記となります。
- 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
- 被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であること
- 退職日において出勤していないこと
この様な要件を満たしますと、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金を退職後も継続して受けることができます。
傷病手当金との調整
様々な理由で傷病手当金を受給しつつ、産前産後休業に入る方がいらっしゃいます。
この様な方は傷病手当金と出産手当金の両方支給要件に該当する場合があります。
この様な場合、出産手当金が優先されます。
但し、傷病手当金と出産手当金それぞれ支給日額が異なる場合があり、出産手当金が傷病手当金よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
健康保険給付について
出産には非常にお金がかかります。
分娩までの通院や検査、分娩費用、その後の検査費用等、さらには出産する方自身が会社を休んで給与の支給が無くなります。
共働き世帯とはいえ、一方の給与支給が無くなるということは、これから子育てという未知の出来事を迎えるにあたり、経済的にも精神的にも不安な状態になります。
そのような中で、分娩費用に充てられる出産育児一時金、産前産後休業中の出産手当金および保険料免除により、経済損失を緩和でき、お金の面では安心して出産、子育てに臨めるようになっております。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
子育て期間中に発生する手続きについてもオフィスステーションで対応可能です。
給付金関係の手続きを行う場合は、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。
その他の手続きについても、電子申請を活用することによって、業務効率化、コスト削減を行うことができます。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください
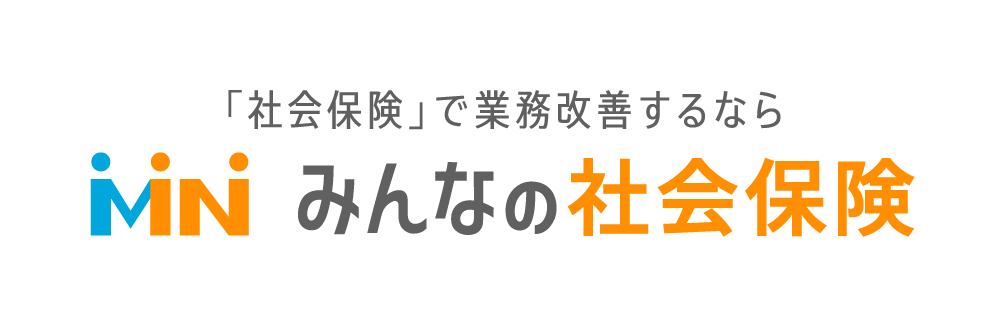
.jpg)