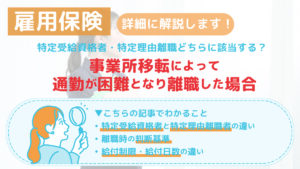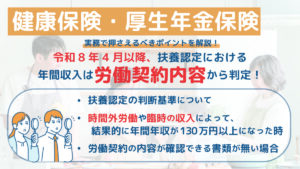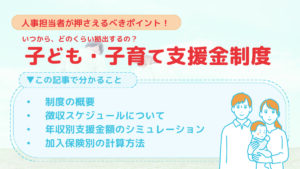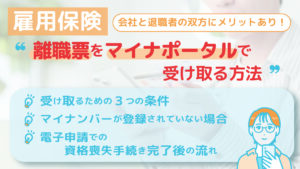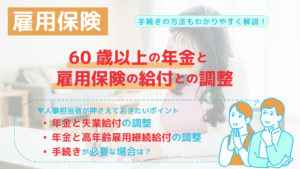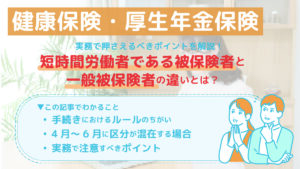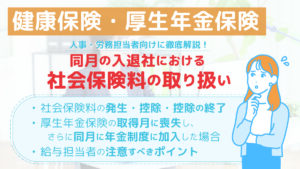育児休業終了後はどんな手続きが発生する?雇用保険、社会保険に関する手続きを詳細に解説します!
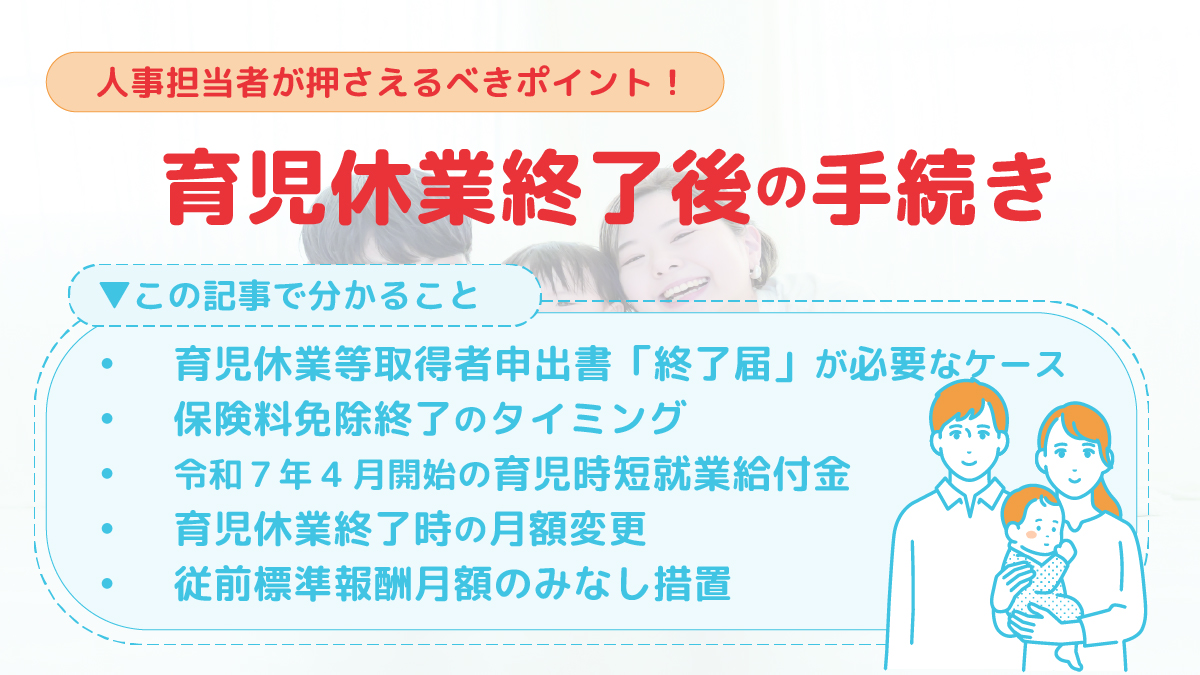
これまで、産前産後休業から育児休業中の雇用保険・社会保険手続きを見ていきました。
今回は育児休業終了後の雇用保険・社会保険手続きを見ていきたいと思います。
社会保険 育児休業等取得者申出書終了届
育児休業中は社会保険料が免除となっておりました。
育児休業が終了となりましたら、免除を解除するため、育児休業等取得者申出書終了届を年金機構事務センターに提出します。
※育児休業を開始した際に育児休業等取得者申出書に記載した終了日と同日に育児休業が終了した場合には、終了届の提出は不要です。
提出が完了いたしますと、社会保険料の免除が解除されますので、給与計算において社会保険料の徴収を忘れずに行いましょう。
保険料免除となる期間は、育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで免除となります。育児休業終了日によって、保険料免除の最終月が異なりますので、保険料徴収開始にあたっては注意が必要です。
- 11月20日に育児休業終了・・・10月分までの社会保険料免除・・・11月分から徴収開始
- 11月30日に育児休業終了・・・11月分までの社会保険料免除・・・12月分から徴収開始
雇用保険 育児時短就業給付金
育児休業が終了となりますと、短時間勤務を選択する場合が多いです。
しかし、短時間勤務を行いますと、給与も減額になってしまいます。
このような懸念を和らげるため、短時間勤務によって減少した給与を補填する育児時短就業給付金が2025年4月から開始されました。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的としています。
要件
受給資格の要件
- 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
受給する際の各月の要件
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給額
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%
ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額(※)を超えないように、支給率が調整されます。
※賃金額:育児休業給付の支給に用いた賃金月額、こちらが無い方は育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金の総額を180で除した額
支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(2025年8月1日からは471,393円)以上であるときには、支給が行われません。支給限度額は毎年8月1日に見直しが行われます。
手続き
原則として、経過した2つの支給対象月(※)について、1回行いますますので、2か月に1回行うこととなります。
※支給対象月:育児時短就業を開始した日の属する月からの各月を指します。
10月分・11月分を12月に申請、12月分・1月分を2月に申請
手続きについては2種類ございます。
育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を事業所管轄のハローワークへ申請します。
添付書類
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則 等が必要です。
育児休業給付の対象となる育児休業がない場合
(育児休業を取らずに短時間勤務を取った夫 等)
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を事業所管轄のハローワークへ申請します。
添付書類
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則 等の他、
育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等)が必要です。
社会保険 育児休業等終了時報酬月額変更
育児休業が終了し復帰しますと、短時間勤務になる方が多く、または残業の減少により、休業前の給与に比べ、給与が低下します。
給与低下に合わせ、社会保険の標準報酬月額を下げる月額変更を行いますが、通常の月額変更とは異なり、要件を満たしやすいような内容となっております。
要件
- 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
- 前記支払基礎日数17日(短時間労働者は11日)以上の平均額の標準報酬月額が、休業前の標準報酬月額と比べ、1等級以上の差が生じていること。
- 育児休業終了時に3歳未満の子を養育している被保険者または70歳以上被用者であること。
通常の月額変更では、3カ月各月全てにおいて支払基礎日数17日(短時間労働者は11日)以上が必要であり、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていることが要件となりますが、こちらに比べ育児休業終了時の月額変更は要件が緩和されております。
通常の月額変更は該当したら手続きを行わなければなりませんが、育児休業等終了時報酬月額変更は任意となっており、手続きの際には被保険者・70歳以上被用者の意思確認が必要です。
標準報酬月額が下がることにより社会保険料が安くなりますが、傷病手当金や出産手当金の金額も安くなる等の不利益が生じる可能性があるためです。
そのため、申請書に申出者(被保険者・70歳以上被用者)の意思確認のチェック欄が設けられております。
なお、産前産後休業後に復帰する方について、同じ仕組みで産前産後休業終了時の月額変更があります。
手続き
健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届を年金機構事務センターに提出します。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないように、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づいた年金額を受け取ることができる仕組みです。
例をあげますと、養育する前(産前産後休業に入る前等)の標準報酬月額が30万円、職場復帰後は短時間勤務となり、月額変更により標準報酬月額が22万円に下がった場合、納める保険料は標準報酬月額22万円分ですが、将来の年金計算には標準報酬月額30万円が用いられることとなります。
育児という理由により、やむを得ず標準報酬月額が下がる場合でも、通常勤務していた水準の標準報酬月額で年金に反映する仕組みであり、安心した職場復帰を促す特例です。
要件
- 3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方
(退職し、転職先でも該当します)
特例期間
- 3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月まで
手続き
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書を年金機構事務センターに提出します。
出産・育児に関する制度を理解しましょう!
ここまで複数回にわたり、産前産後休業から育児休業、そして育児休業終了後の雇用保険・社会保険にかかる保険料免除、給付金等をご紹介いたしました。
深刻な少子化、共働き家庭が増加する中、育児と仕事の両立を支援するため、2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」が新たに創設され、さらに手厚い支援体制が構築されました。
これら雇用保険・社会保険制度以外にも、育児介護休業法において2025年4月・10月からは、子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限拡大、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加、育児のためのテレワーク導入、育児休業取得状況の公表義務適用拡大、柔軟な働き方を実現するための措置・個別の周知・意向確認、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が追加されました。
産休・育休・職場復帰という流れの中で、会社は様々な手続きを要するため、整理して一つ一つクリアしていく必要がございます。
なお、ここまでご紹介した雇用保険・社会保険にかかる保険料免除、給付金等については、ご紹介しきれない細かな事項がありますので、各制度のURLを添付いたします。
手続きの際にご参考にしていただければと思います。
産前産後休業取得者申出書/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140326-01.html
育児休業等取得者申出書/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
出産育児一時金/協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145
出産手当金/協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148
育児休業等給付(出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
育児休業等終了時報酬月額変更/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140626-01.html
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
育児休業給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。
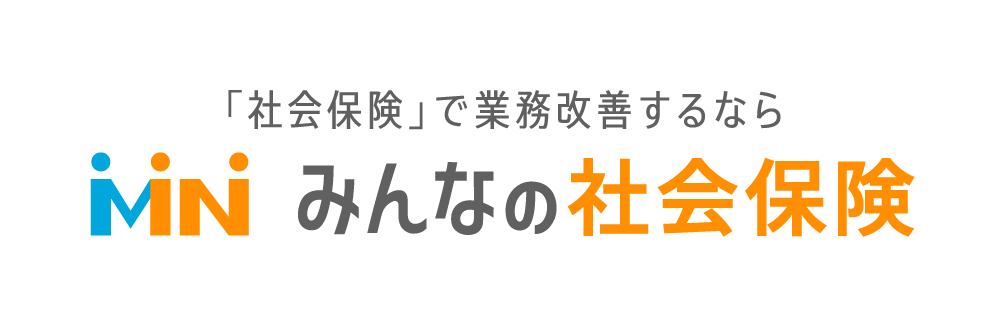
.jpg)