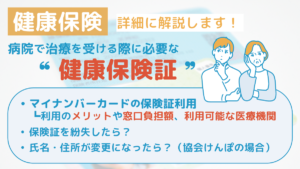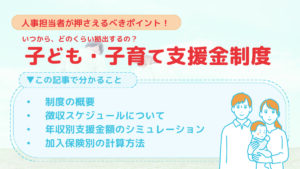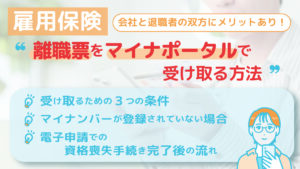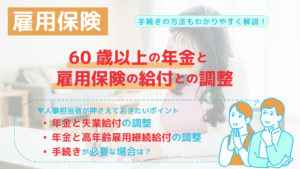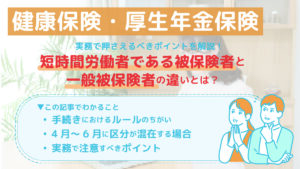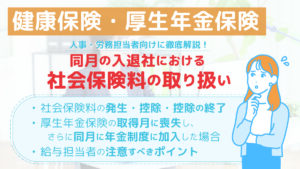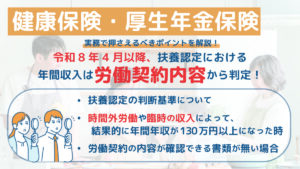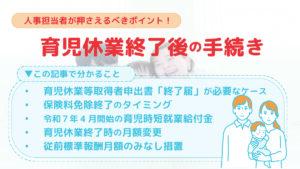厚生年金保険、健康保険に関する高齢者の手続きについて、詳細に解説します!
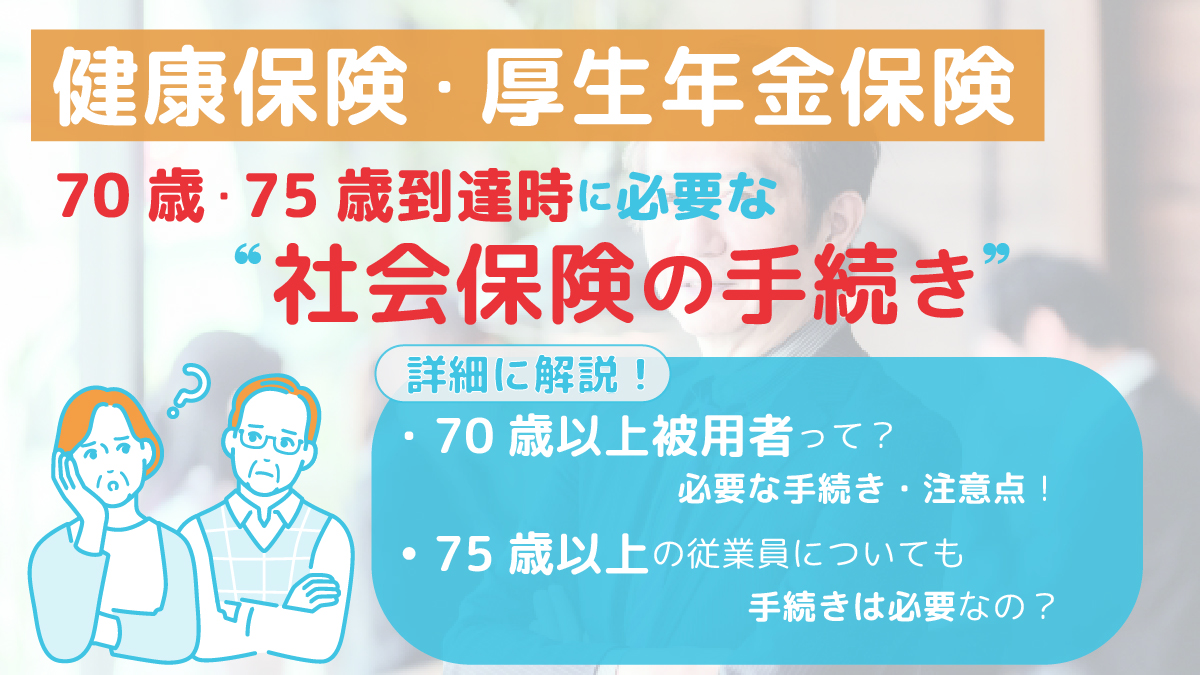
今回は70歳以上の厚生年金保険、健康保険に関する手続きについて見ていきたいと思います。
70歳、75歳に到達した際に必要な手続き、不要な手続き等、詳細に解説しています。
ぜひお読みください。
高齢化について
令和3年10月の日本の人口1億2,550万人の内、65歳以上の人口は3,621万人となり、総人口に対して28.9%を占めております。
約50年前の昭和45年では7%程でした。この半世紀の間に高齢化が進み、今後もさらに高齢化が進む見込みで、令和47年には総人口に対して38.4%になると推計されております。
高齢化が進みますと、当然高齢者が働く機会が増えてきますので、それに伴う労働関係制度の整備が必要となります。
近年では老齢年金支給開始年齢の引き上げ(60歳→65歳)、65歳までの雇用確保、70歳までの雇用確保の努力義務、等があげられます。
定年を経て雇用継続に至る場合には、このような場合に適した労働契約書や就業規則の整備も必要になろうかと思います。
高齢者を就労させる場合は、注意しなければならない点がいくつかございますが、厚生年金保険の手続きにつきましても注意する点がございます。
(高齢者人数・割合について 参考:令和4年度版 高齢社会白書/内閣府)
70歳到達時 厚生年金保険の喪失
厚生年金保険においては、70歳になると被保険者資格を喪失します
資格喪失日は70歳誕生日の前日となります。
こちらの資格喪失手続きは会社で行う必要は無く、年齢により自動的に資格喪失手続きが行われます。
資格喪失が終わりましたら、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」が会社宛に送付されます。
70歳到達時 被用者該当
70歳になると、資格喪失が行われ、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」が会社宛に送付されますが、同時に「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送付されます。
被用者該当とは、厚生年金保険に加入するような働き方の場合に、70 歳以上被用者として標準報酬月額相当額の登録を行うことです。
70歳以上の方が老齢厚生年金と給与を得ている場合、年金と給与・賞与の金額によって老齢厚生年金の金額が一部または全部支給停止になる仕組みとなっております。
そのため、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、標準報酬月額相当額を登録することになります。
70 歳以上被用者該当とともに、今まで登録されていた標準報酬月額がそのまま標準報酬月額相当額として登録されます。
70歳到達時に給与が変わる場合には70歳到達届に該当となる報酬額を記入し提出します。
70歳と同時に働く日数・時間が減り、厚生年金保険加入要件に満たなくなる場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出となります。
70歳以上被用者に関する手続き
70歳以上被用者該当となりますと、老齢厚生年金の支給停止のために、標準報酬月額相当額が登録されます。
こちらの標準報酬月額相当額は被保険者の標準報酬月額と同じく、定時決定や随時改定の対象となり、賞与を支給した場合は賞与支払届の届出が必要になります。
この様に通常の被保険者と同じように報酬に関する届出が必要となります。
下記は70歳以上被用者に関する手続きとなります。
・70歳以上被用者算定基礎届
・70歳以上被用者月額変更届
・70歳以上被用者賞与支払届
・70歳以上被用者不該当届(75歳未満の場合、健康保険の喪失も同時に行う)
こちらの手続きの内容は、通常の被保険者と同じです。
例えば月額変更届の場合には、固定的賃金が変動した月から3か月の平均を取り、2等級以上変化していること、各月の賃金支払基礎日数が17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)であることを確認し、月額変更該当であれば届出を行います。
こちらにより、標準報酬月額相当額が変わり、老齢厚生年金の支給停止額に反映されます。
70歳以上 中途採用者
70歳以上の中途採用の方が厚生年金保険に加入する要件を満たすと、被用者該当の届出が必要となります。
70歳以上75歳未満の方であれば健康保険資格取得手続きと同時に行いますが、75歳以上の方ですと、健康保険に加入いたしませんので、厚生年金保険70歳以上被用者該当届のみの届出が必要となります。
70歳以上被用者に該当となりますと、各種報酬に関する届出(算定基礎届・月額変更届・賞与支払届)が必要になります。
75歳 健康保険資格喪失
75歳になると健康保険被保険者資格が喪失となります。
資格喪失日は75歳誕生日当日となります(厚生年金保険の70歳到達による喪失は誕生日の前日でした)。
健康保険の喪失手続きは会社で行う必要があります。健康保険資格喪失届を年金機構に届出て手続きを行います。
なお、75歳になりますと後期高齢者医療制度へ加入となり、こちらで発行された健康保険証を使用します。
75歳以上 被保険者ではない方
75歳以上で厚生年金保険の加入要件を満たすような働き方の方は、年齢から厚生年金保険・健康保険どちらも被保険者ではありませんが、70歳以上の被用者として該当している状態となります。
健康保険の被保険者であった75歳になるまでについては、給与から健康保険料が控除され、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を届出しておりますので、こちらの届出と同時に70歳以上の各届出を行っておりましたが、75歳以上になり健康保険を喪失することにより、健康保険料の控除が無くなります。
健康保険・厚生年金保険の被保険者としては管理されない状態となります。
しかし70歳以上の被用者は報酬の届出が必要ですので、変わらず算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を届出することとなります。
そのため、70歳以上の被用者として管理し、各種届出が漏れなく行われる状態にすることが必要となります。
こちらが漏れてしまいますと、支給される年金額に影響が生じます。
70歳以上 高齢任意加入被保険者
厚生年金保険は70歳までの加入となりますが、70歳以上でも加入できる場合がございます。
要件としては老齢年金を受けられる加入期間(10年)が無い方となります。
この様な方は70歳以上でも老齢年金を受けられる加入期間を満たすまで、任意に厚生年金保険に加入することができます。
例えば、海外の70歳以上の方が日本に来て、厚生年金保険の適用事業所で仕事をし始める場合です。
こちらの方はずっと住んでいた国から年金が支給されない場合、何も年金として支給されるものはありません。
また、元々日本に住んでいて数年間年金保険料を支払っていましたが、その後海外に住み始め、70歳以後帰国する場合等です。
あくまで老齢年金を受けることができない方が受けることができる加入期間まで加入できる制度ですので、年金の金額を任意に増やすために加入する目的ではありません。
手続きは「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を年金機構へ提出して行います。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
厚生年金、健康保険に関する手続きついてはオフィスステーションで電子申請可能です。
オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、進捗管理や公文書管理を行うこともできますので、ぜひご検討ください。
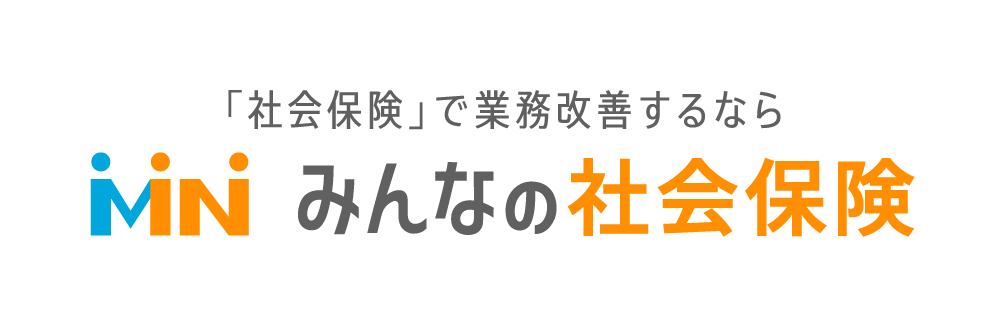
.jpg)