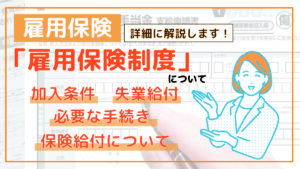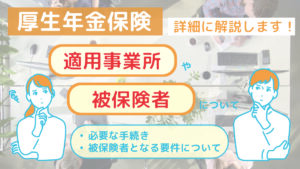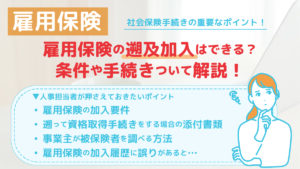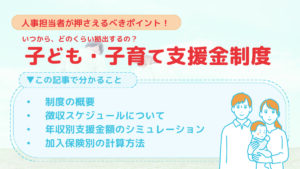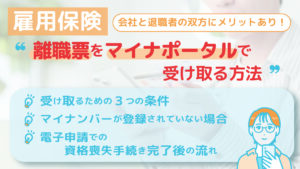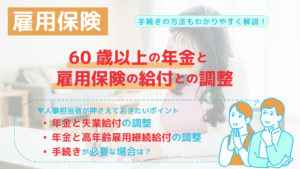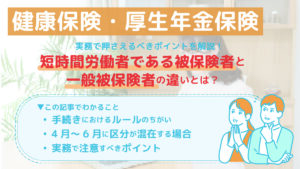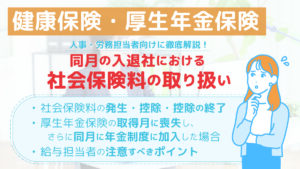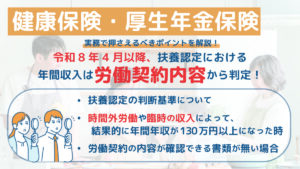労災保険の給付について 条件、内容を詳細に説明します!
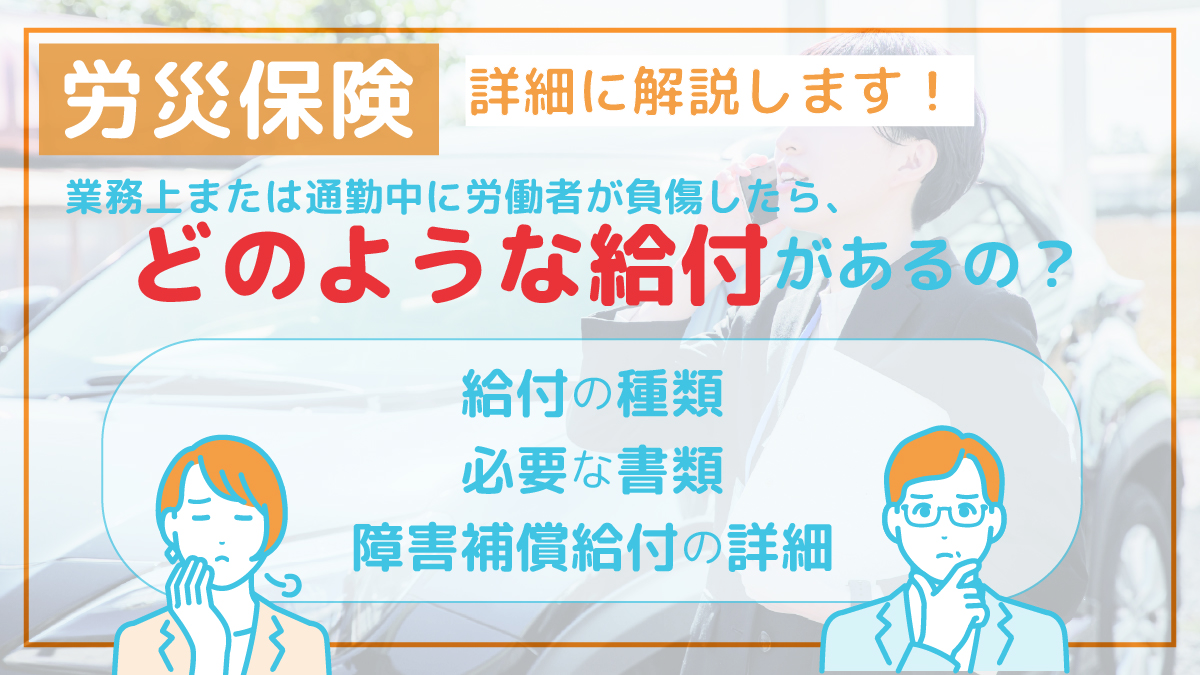
今回は労災保険の給付についてより詳細にお話しさせていただきます。
どのような場合に、どのような給付が行われるのか?
わかりやすく説明しておりますので、ぜひお読みください。
療養(補償)給付
給付の内容
労災指定病院・薬局等で、症状が治癒(症状固定※)されるまで、下記の支給を無料で受けることできます。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
※医学上、一般に認められた医療を行っても、それ以上医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
手続き
「療養の給付」と、「療養の費用の支給」に分かれます。
療養の給付
労災指定病院・労災指定薬局で治療、薬剤の提供を受けた場合
<必要書類>
~業務災害~
・様式第5号「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」
~通勤災害~
・様式第16号の3「療養給付たる療養の給付請求書」
<医療機関の窓口での支払い>
なし
~複数事業労働者の場合~
様式第5号裏面、もしくは様式第16号の3裏面の「その他就業先の有無」に記入が必要です。
<提出先>
労災指定病院・労災指定薬局
療養の費用の支給
労災指定病院・労災指定薬局ではない所で治療を受けた場合
<必要書類>
・様式第7号(1)「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」
※医師の証明が必要です
・領収書
整骨院などで柔道整復師の施術を受けた場合
<必要書類>
・様式第7号(3)「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」
※柔道整復師の証明が必要です
・領収書
<医療機関の窓口での支払い>
あり。一旦全額を負担し、申請後、後日本人の口座へ振込となります。
~複数事業労働者の場合~
様式第7号裏面の「その他就業先の有無」に記入が必要です。
<提出先>
労働基準監督署
【病院・薬局を変更した場合】
<必要書類>
・様式第6号「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」
~複数事業労働者の場合~
様式第6号裏面の「その他就業先の有無」に記入が必要です。
<提出先>
労災指定病院・労災指定薬局
【時効】
療養の給付は、現物給付のため時効はありませんが、療養の費用の支給は、費用を支出した日ごとに、その日の翌日から2年が時効となります。
休業(補償)給付
【給付の内容】
業務上の事由または通勤災害による傷病のため、労働することができず、賃金を受けられない場合、4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。休業特別支給金と合わせて、休業前の賃金の約80%の給付となります。
※通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されます。
休業(補償)給付:給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数
※給付基礎日額:業務災害もしくは通勤災害が発生した日、または診断によって病気が確定した日の直前3ヵ月の給与の総額を、その期間の歴日数で割った額になります。
【手続き】
~業務災害~
・様式第8号「休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書」
※医師の証明が必要です
・様式第8号の別紙1、2
~通勤災害~
・様式第16号の6「休業給付支給請求書」
※医師の証明が必要です
・様式第16号の6の別紙1、2
~複数事業労働者の場合~
・様式第8号裏面、もしくは様式第16号の6裏面の、「その他就業先の有無」に記入が必要です。
・様式第8号または様式第16号の6で記載した事業場以外の事業場についての別紙1から別紙3を添付。
<提出先>
労働基準監督署
【時効】
休業の日ごとに、その翌日から2年
傷病(補償)年金
【給付の内容】
傷病等級に応じて、傷病(補償)等年金、傷病特別支給金(一時金)、傷病特別年金が支給されます。
| 傷病等級 | 傷病(補償)等年金 | 傷病特別一時金 | 傷病特別年金 |
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
※算定基礎日額:業務災害もしくは通勤災害が発生した日、または診断によって病気が確定した日以前1年間に受けた賞与の総額を365で割った額になります。
【手続き】
療養開始後1年6ヵ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1ヵ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署に提出します。
また、療養開始後1年6ヵ月を経過しても、傷病(補償)等年金の支給要件に該当しない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付の申請の際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を合わせて提出します。
<提出先>
労働基準監督署
<休業(補償)給付との関係>
傷病(補償)給付は、休業(補償)給付の代わりに支給されるものになりますので、傷病(補償)給付が支給される場合、休業(補償)給付の支給はありません。
一方、傷病(補償)給付の要件に該当しない場合は、引き続き、休業(補償)給付が支給されます。
【時効】
監督署長の職権により移行されるため、時効はありません。
障害(補償)給付
【給付の内容】
業務または通勤災害により、身体に一定の障害が残ったとき、以下の障害等級に該当する場合に支給がされます。
| 障害 等級 | 障害(補償)等給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 | ||||
| 第1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 一時金 | 342万円 | 年金 | 算定基礎日額の313日分 | – | – |
| 第2級 | 年金 | 給付基礎日額の277日分 | 一時金 | 320万円 | 年金 | 算定基礎日額の277日分 | – | – |
| 第3級 | 年金 | 給付基礎日額の245日分 | 一時金 | 300万円 | 年金 | 算定基礎日額の245日分 | – | – |
| 第4級 | 年金 | 給付基礎日額の213日分 | 一時金 | 264万円 | 年金 | 算定基礎日額の213日分 | – | – |
| 第5級 | 年金 | 給付基礎日額の184日分 | 一時金 | 225万円 | 年金 | 算定基礎日額の184日分 | – | – |
| 第6級 | 年金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 192万円 | 年金 | 算定基礎日額の156日分 | – | – |
| 第7級 | 年金 | 給付基礎日額の131日分 | 一時金 | 159万円 | 年金 | 算定基礎日額の131日分 | – | – |
| 第8級 | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 | 一時金 | 65万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の503日分 |
| 第9級 | 一時金 | 給付基礎日額の391日分 | 一時金 | 50万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の391日分 |
| 第10級 | 一時金 | 給付基礎日額の302日分 | 一時金 | 39万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の302日分 |
| 第11級 | 一時金 | 給付基礎日額の223日分 | 一時金 | 29万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の223日分 |
| 第12級 | 一時金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 20万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の156日分 |
| 第13級 | 一時金 | 給付基礎日額の101日分 | 一時金 | 14万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の101日分 |
| 第14級 | 一時金 | 給付基礎日額の56日分 | 一時金 | 8万円 | – | – | 一時金 | 算定基礎日額の56日分 |
<併合繰上>
2つ以上の障害がある場合には、原則「重い方」の障害等級となりますが、次の場合には、障害等級の繰上げが行われます。
・第13級以上の障害が2以上あるとき・・・重い方を1級繰上げ
・第8級以上の障害が2以上あるとき・・・重い方を2級繰上げ
・第5級以上の障害が2以上あるとき・・・重い方を3級繰上げ
※併合繰上げをした結果、8級以下である場合であって、各々の障害等級の合算額が、繰上げられた等級の額に満たないときは、各々の障害等級の合算額の支給となります。
<労災と厚生年金の調整>
障害厚生年金も受けられるときは、障害厚生年金は全額支給されますが、労災の障害(補償)年金の一部が減額となります。
【手続き】
~業務災害~
・様式第10号「障害補償給付 複数事業労働者障害給付支給請求書」
・診断書(※所定の用紙)
~通勤災害~
・様式第16号の7「障害給付支給請求書」
・様式第16号の7(別紙)
・診断書(※所定の用紙)
<診断書料を申請する場合>
~業務災害~
・様式第7号「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」
・診断書の領収書
~通勤災害~
・様式第16号の5「療養給付たる療養の費用請求書」
・診断書の領収書
<提出先>
労働基準監督署
【時効】
傷病が治癒した日の翌日から5年
障害(補償)年金前払一時金
【給付の内容】
障害(補償)年金を受給する方が、障害等級に応じて1回に限り、前払いを受けることができます。
前払い一時金の額は、障害等級に応じた希望の額を選択することができます。
| 障害等級 | 前払一時金の額 |
| 第1級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の200日分、400日分又は560日分 |
【手続き】
障害(補償)給付の請求と同時に、以下を提出します。
・年金申請様式第10号「障害補償年金・障害年金前払一時金請求書
※治癒した翌日から2年以内で、障害(補償)年金の支給決定の通知があった日の翌日から1年以内であれば、障害(補償)年金を受けた後でも請求をすることができます。
<提出先>
労働基準監督署
【時効】
傷病が治癒した日の翌日から2年
障害(補償)年金差額一時金
【給付の内容】
障害等級に応じて定められている一定額から、既に支給された障害(補償)等年金と、障害(補償)等年金前払一時金の合計額を差し引いた額が、下記の遺族の順で支給されます。
<遺族の範囲>
(1)労働者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(2)(1)に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
| 障害等級 | 障害(補償)等年金差額一時金 | 障害特別年金差額一時金 |
| 第1級 | 給付基礎日額の1,340日分 | 算定基礎日額の1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の1,190日分 | 算定基礎日額の1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の1,050日分 | 算定基礎日額の1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の920日分 | 算定基礎日額の920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の790日分 | 算定基礎日額の790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の670日分 | 算定基礎日額の670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の560日分 | 算定基礎日額の560日分 |
【手続き】
・様式第37号の2「障害(補償)等年金差額一時金支給請求書 障害特別年金差額一時金支給請求書」
・事実婚の場合、請求人と死亡した労働者との事実婚を証明する書類
・請求人と死亡した労働者との身分関係を証明する書類
<提出先>
労働基準監督署
【時効】
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
労災保険に関する申請業務は電子申請が行えませんが、書類についてはオフィスステーションを利用し作成しております。
手書きで書類を作成しようとすると、多くの時間がかかりますが、電子的に書類を作成すると、時間的メリットがあり、修正もとても簡単ですので、ぜひご検討ください。
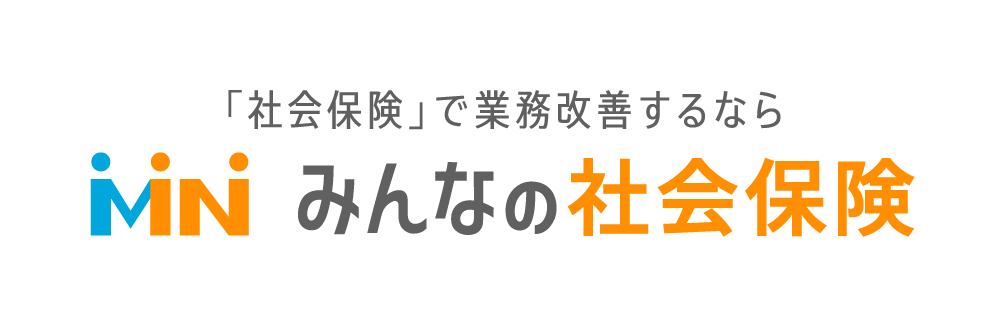
.jpg)